ナレッジベース
スタートアップ企業に転職する前に知っておきたいこと|成長環境でキャリアを築く方法
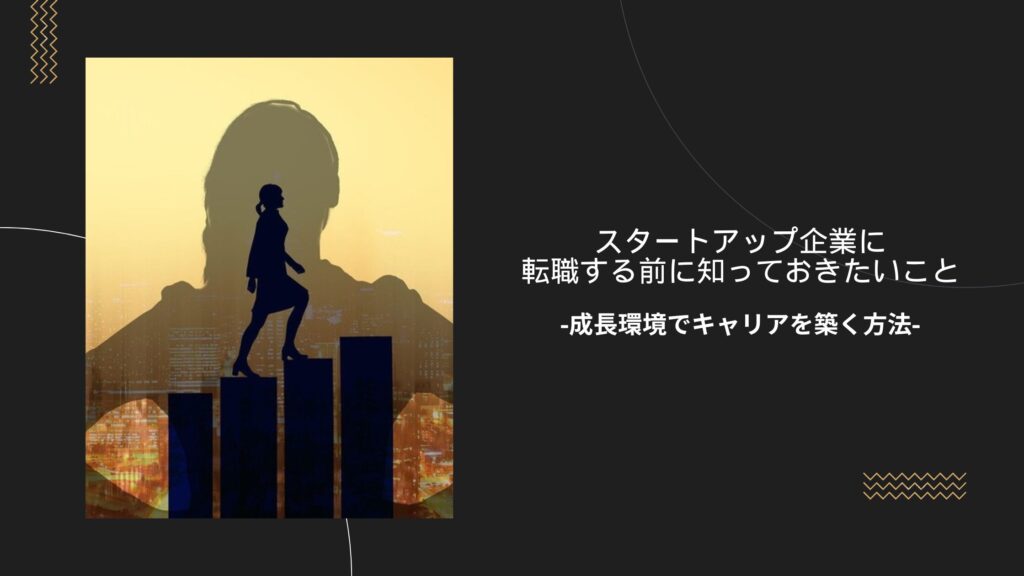
2025.07.09
スタートアップ
スタートアップとは──定義とベンチャー企業との違い
スタートアップの定義とは?
「スタートアップ」と聞くと、革新的なプロダクトを開発している急成長中の企業を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。実際、そのイメージはあながち間違っていません。ただし、スタートアップの本質を突き詰めると、「不確実性の高い市場で、再現性のあるビジネスモデルを短期間で確立・拡大しようとする組織」と定義されます。
スタートアップという言葉の起源はアメリカのシリコンバレー。特にテック領域の企業群がこのラベルで語られることが多く、リスクを取りながら新市場に挑戦する姿勢が共通しています。
日本国内においても、AI、SaaS、ヘルスケア、Fintech、ディープテックなどを中心に多くのスタートアップが生まれ、VCやPEファンドの支援を受けながら急成長を遂げています。

ベンチャー企業との違い
「スタートアップ」と混同されがちな言葉に「ベンチャー企業」があります。日本語ではしばしば同義に扱われますが、厳密には異なる概念です。
| 観点 | スタートアップ | ベンチャー企業 |
| 目的 | 短期間でのスケール・EXIT | 安定成長やニッチ市場の確保 |
| ビジネスモデル | 未確立で不確実性が高い | すでにある程度成立している |
| 資金調達 | VC、PE、エンジェルなど外部資金依存 | 自己資金や銀行融資も多い |
| 組織体制 | 少人数、フラット、変化に柔軟 | 比較的ヒエラルキーが明確 |
このように、スタートアップは短期的な成長とスケールを最優先するのに対し、ベンチャー企業は中長期での市場定着や安定的な成長を志向する傾向があります。
中小企業・大企業との違い
一方、スタートアップと中小企業や大企業の違いは、規模や資金力だけでなく、経営思想と組織文化においても大きな乖離があります。
中小企業との違い
- 中小企業:既存産業の中で着実に商売を継続。地元密着やリピーター重視。
- スタートアップ:未開拓市場への挑戦が前提。1→10よりも、0→1に重きを置く。
大企業との違い
- 大企業:組織規模が大きく、意思決定に時間を要する。明確な職務分掌と階層構造。
- スタートアップ:意思決定が速く、一人が複数の役割を担うことも日常茶飯事。職種の境界も曖昧。
これらの違いは、求職者にとっては「安定志向」か「挑戦志向」かを見極める判断材料ともなります。
スタートアップの特徴3選
- 短期間での圧倒的成長を目指す:3〜5年でのIPOやM&Aを見据え、資金・人材を一気に投下して市場を取りに行きます。
- プロダクトアウト型が多い:まだニーズが顕在化していない市場に、独自技術やアイデアで切り込むケースが多い。
- 組織がフラットで裁量が大きい:年齢・経験に関係なく成果を出せば抜擢される環境があります。
なぜ今「スタートアップ」が注目されるのか?
- 政府の支援強化:スタートアップ育成5か年計画やNEDO補助金など政策支援が拡大中。
- 人材の流動性向上:大企業からスタートアップへの“越境転職”が当たり前になりつつある。
- 社会課題解決の担い手:脱炭素、医療格差、地方創生など、難題に挑む企業が多い。
時代が大きく変わるいま、スタートアップは「キャリアの最前線」であり、「社会変革の最前線」でもあるのです。
次章では、そんなスタートアップで働くことの「メリットとリスク」について、リアルな視点で深掘りしていきます。
スタートアップで働くメリットとリスク
スタートアップで働く魅力とは?
スタートアップに惹かれる人は年々増えています。その最大の理由は「自分の力で会社や社会を変えていける」という実感を得やすいからです。大企業と比べて年次・役職に関係なく発言や提案が歓迎され、実行に移せるスピードも桁違いです。
1. 圧倒的な成長機会
スタートアップでは、未整備な部分が多く、自ら考えて動くことが求められます。その分、担当範囲は広く、経営視点を含む多角的なスキルが身につきやすいです。数年で事業責任者に昇進するケースもあり、他社では得難い「成長実感」が得られるでしょう。
2. 裁量の大きさとスピード感
意思決定までのフローが短く、顧客の声や市場変化を受けて素早く改善・実行が可能。自身の提案が即座に採用され、売上やKPIに直結する手応えを感じやすい環境です。
3. 経営層との近さ
経営陣と物理的にも心理的にも距離が近く、経営判断のプロセスを肌で学べます。VCや投資家とのやりとりに同席するチャンスも多く、将来起業を志す人にとっては絶好の環境といえるでしょう。
4. 社会課題に対する当事者意識
脱炭素、地方創生、医療DXなど、社会的インパクトが高い事業を手がけているスタートアップも多く、「誰かの役に立っている」という実感が日々の仕事から得られるのも魅力です。
スタートアップならではのリスクとは?
一方で、スタートアップで働く上で無視できないのが「不確実性」と「高負荷環境」です。憧れや希望だけで飛び込むと、ミスマッチに苦しむケースもあります。
1. 経営リスクと雇用の不安定さ
資金繰りに苦しむケースや、資金調達が思うように進まず事業が継続できないリスクも。売上がなくてもランウェイ(資金が尽きるまでの期間)で動いているフェーズでは、急なリストラや組織変更も珍しくありません。
2. 職務の流動性と役割の曖昧さ
職種の垣根が低く「営業+マーケ+CS+企画」といったハイブリッドな動きを求められることも。固定された職務範囲で働きたい人にとってはストレスになり得ます。
3. 業務量とワークライフバランスの崩れ
成長フェーズによっては、土日対応や深夜対応が発生するケースもあります。ミッションへの熱量が高い組織文化ゆえに「仕事が生活の中心」になるリズムへの適応力が求められます。
4. 福利厚生・制度の未整備
大企業と比べて評価制度や教育体制、福利厚生が整っていない企業もあります。特に20代〜30代の若手で、育成前提でのジョインを希望する方は、教育投資が十分な企業かを見極める必要があります。
スタートアップで成功する人の共通点とは?
- 変化耐性がある:毎月ルールが変わる環境でも楽しめる柔軟性
- 自律的に動ける:指示を待つのではなく、自分で課題を見つけて動ける
- 挑戦を恐れない:前例のないタスクにも臆せずトライできる胆力
- チームと共に走れる:孤軍奮闘ではなく、仲間と共に“共創”できる
これらの要素を備えた人材は、スタートアップの変化とスピードを成長の糧に変えられるでしょう。
スタートアップ転職に向いている人・向いていない人の特徴
スタートアップへの転職を考える際に大切なのが、「自分がその環境に向いているか」を見極めることです。憧れやイメージだけで飛び込むのではなく、自分の志向性・行動特性とスタートアップの特性がマッチするかどうかを確認することが、転職の成否を大きく左右します。

スタートアップに向いている人の特徴
1. 変化を楽しめる柔軟性の高い人
スタートアップでは、日々起こる変化や意思決定のスピードについていく必要があります。戦略の方向転換や組織改編、プロダクトの仕様変更などは日常茶飯事。それらを「想定外」としてストレスに感じるのではなく、「面白い」「成長のチャンス」と捉えられる人は向いています。
2. 自ら動ける当事者意識がある人
マニュアルや役割が細かく整備されていないため、自ら課題を見つけて動く“自走力”が求められます。言われたことだけをやるのではなく、目的思考で状況を整理し、次にやるべきことを自ら定義できる人が活躍しやすいです。
3. 成長欲が強く、挑戦を楽しめる人
未経験領域にも飛び込み、失敗しても学びに変えられるマインドを持つ人は、スタートアップの土壌で急成長できます。特に20代で「経営視点を持ちたい」「意思決定に関与したい」という熱量の高い人は、環境のポテンシャルを最大限活かせるでしょう。
4. 人とチームを尊重できる人
変化とスピードのある環境では、意見のぶつかり合いも日常的です。その中でチームと建設的な対話ができる人、相手の背景を想像して行動できる人は、組織の信頼を得て前に進みやすくなります。
スタートアップに向いていない人の特徴
1. 安定やルールを重視する人
評価制度や職務範囲、業務フローが整った環境を好む人には、スタートアップの曖昧さや変動の大きさがストレスになります。「毎週やることが変わる」ことを苦痛に感じるなら、他の選択肢の方が合っているかもしれません。
2. 指示待ち・受け身のスタンス
スタートアップでは「待っていても何も起きない」ことが多く、自ら提案・実行してこそ仕事が進みます。自発性のない姿勢は、本人も周囲も苦しくなる要因になります。
3. 完璧主義・準備主義
スピードを重視する現場では、「まずやってみる」「走りながら修正する」文化が根付いています。完璧に準備が整わないと動けないタイプの人は、成果を出しづらくなってしまいます。
4. 上下関係や肩書きにこだわる人
スタートアップでは、年齢や肩書きよりも「実行力」や「成果」で評価されます。上下関係を気にしすぎたり、職位によって動き方を変える人は、カルチャーのフィットが難しい傾向にあります。
自己診断チェックリスト
以下の質問に「はい」が多ければ、スタートアップ転職に向いている可能性が高いです。
- 変化がある方がワクワクする
- 新しい役割に挑戦するのが好きだ
- 指示を待たずに自分で動くのが得意だ
- 「これ、やってみたい」が口癖だ
- 転職先で急成長したいという思いがある
- 組織の成長に貢献することがやりがいだと感じる
次章では、スタートアップでのキャリア形成の具体的なパターンやロールモデルをご紹介します。
スタートアップでのキャリア形成パターンとロールモデル
スタートアップへの転職をキャリアの「最終目的」とする人もいれば、「ステップ」として捉える人もいます。本章では、スタートアップで形成される多様なキャリアパターンと、実在するロールモデルを紹介し、どのような未来が描けるのかを具体的に解説します。
1. スタートアップでのキャリアの考え方:目的か通過点か
スタートアップ転職の動機はさまざまです。「CxOを目指したい」「いずれ起業したい」「社会課題を解決する事業に関わりたい」などの明確なビジョンを持つ人もいれば、「裁量が大きい環境で成長したい」「スピード感のある仕事がしたい」といった成長環境志向の人もいます。
ここで重要なのは、スタートアップでの経験が「自分のキャリアをどう広げるのか」を明確にすること。目的が定まっていれば、仮に困難に直面しても、得られる経験を意義あるものとして捉えやすくなります。
2. 代表的なキャリアパターン
パターンA:事業責任者・役員に抜擢される
20代後半〜30代前半で入社後すぐにプロジェクト責任者を任され、1〜2年後には事業部長、さらには執行役員に昇格するケースもあります。成長産業で急拡大しているスタートアップでは、年齢や社歴よりも「結果」と「再現性ある実行力」が重視されます。
パターンB:スタートアップ→メガベンチャー・上場企業へ
「スタートアップで修行した後、大手企業やメガベンチャーへ転職する」という道もあります。事業立ち上げフェーズで培ったハードスキル・ソフトスキルは、大企業の新規事業部門や事業再生部門などで高く評価されます。
パターンC:スタートアップでの経験を活かして起業
創業メンバーや経営陣の意思決定に間近で関わることで、経営感覚や起業ノウハウを学び、その後独立するケースです。「スタートアップでの3年=他社の10年分」と言われるほど、密度の濃い経験が自信と行動力に直結します。
パターンD:複数社スタートアップ経験→専門職で独立
PM・マーケター・ファイナンスなどの専門職で複数のスタートアップに関わり、その後フリーランスや顧問、アドバイザーとして独立するパターン。柔軟な働き方を実現しつつ、高単価での業務委託契約を獲得することも可能です。
3. 実在するロールモデルの紹介
● 29歳で執行役員になった元営業職(女性)
元大手人材会社の営業担当だった女性が、HR系スタートアップへ転職。1年後に営業部長に抜擢され、さらに新規事業の立ち上げを主導し、29歳で執行役員に就任。「裁量とスピード」を武器に、短期間で経営人材へと進化した事例です。
● 大企業からスタートアップに転職し、IPO経験を得たエンジニア(男性)
大手SIer勤務の30代前半男性が、SaaS系スタートアップにジョイン。インフラ構築からプロダクトマネジメントまで幅広く担当し、上場までのプロセスに深く関わった。「スキル以上にビジネス感覚を得たことが、次のキャリアに効いている」と語ります。
4. スタートアップでキャリア形成する際の注意点
- ビジョンの不一致に注意:企業側と自身の方向性に齟齬があると、モチベーションを保つのが難しくなります。
- 役割変化への柔軟性:事業フェーズによって職務が変わることが多いため、変化を前向きに受け入れる心構えが重要です。
- 長期視点のバランス:短期的な成果に追われすぎず、キャリア全体でどんなスキルを積みたいかを意識しましょう。
スタートアップ転職でよくある誤解と注意点
スタートアップ転職を検討する際、正しい情報に基づいた判断が非常に重要です。しかしSNSやネット記事などを通じて、多くの人が「誤解」や「思い込み」に基づいて意思決定をしてしまうこともあります。本章では、よくある誤解をテーマに、それぞれの注意点と、正しい見極め方を解説します。
1. 「未経験でもスタートアップなら何でも挑戦できる」は本当か?
たしかにスタートアップには「ポテンシャル採用」や「未経験でも挑戦できる環境」が整っている企業も存在します。ただし、すべてのポジションで「未経験歓迎」というわけではなく、特にCxO直下の重要なポジションや、限られた人員で成果を出さなければならない職種では、即戦力が求められることが大半です。
注意点:
- 本当に未経験OKかは、**「募集背景」や「企業フェーズ」**を見ることが重要。
- 未経験者に対するフォロー体制(OJT、メンター制度など)の有無もチェックすべきポイント。
2. 「自由でフラットな環境=働きやすい」は誤解のもと
多くのスタートアップが「フラットな組織」「自由な文化」を打ち出しています。しかしそれは、「自律」「成果主義」「スピード重視」の裏返しでもあります。
注意点:
- フラット=楽、ではなく「自己判断・自己責任」が前提。
- 指示待ちタイプや、職務範囲が明確でないと動けない人には負荷が大きい場合がある。
3. 「残業が多い」「休めない」は本当?
スタートアップは業務量が多いというイメージがあります。確かに創業初期やシリーズA〜B前後のタイミングでは、労働集約的な働き方を強いられることもあります。
注意点:
- すべてのスタートアップが激務というわけではない。
- 業界(SaaS/物流Tech/D2Cなど)や職種(BizDev/開発など)によっても負荷は異なる。
- 勤務実態を知るには「社員インタビュー」「Wantedly」「カジュアル面談」などを活用するのが効果的。
4. 「スタートアップ=すぐ潰れるから危ない」は本当か?
もちろん資金繰りや経営不安定のリスクはありますが、全スタートアップが「危険」なわけではありません。
注意点:
- VC・PEファンドの出資状況、売上の伸び、経営陣の過去実績などを調査すること。
- 特に”連続起業家”が代表を務めている企業は成功確率が高い傾向にある。
5. 「スタートアップで働けば何でもスキルが身につく」は正しいか?
広範な経験が積めるのは事実ですが、スキルの「質」と「汎用性」は自分の姿勢と環境次第です。
注意点:
- 雑務に忙殺されてしまう可能性もある。
- 戦略・設計に携われるフェーズかどうかを見極める必要がある。
- キャリアパスとして、次にどこに転職できるかを逆算して設計すべき。
スタートアップ転職を成功に導く情報収集と支援サービス活用法
スタートアップへの転職は、一般的な転職活動とは異なり、スピード感・成長フェーズ・投資状況など、特有の変数が多く存在します。そのため、自身のキャリアを委ねる環境として本当にマッチしているかどうかを見極めるには、徹底した情報収集と信頼できる外部リソースの活用が不可欠です。
本章では、「どのような情報を集めるべきか」「どのような方法で調べるとよいか」「誰に相談すべきか」という3つの視点から、スタートアップ転職を成功させるための実践的なノウハウを解説します。
1. スタートアップ企業選びに必要な情報項目
転職先候補の企業を調査する際には、以下の観点を網羅的にチェックすることが重要です。
- 企業の成長フェーズ(シード/シリーズA/B/C〜)
- 資金調達の実績(投資元、調達額、直近の資金調達時期)
- プロダクト・サービスの完成度・将来性
- 経営陣のバックグラウンドと過去実績
- カルチャー・価値観(ミッション/バリュー)
- 社員数と増減トレンド/離職率
- ポジションの裁量範囲・ミッションの明確さ
- 評価制度や報酬体系(ストックオプション有無含む)
特に資金調達と経営陣の実績は、企業の継続性や今後の伸び代を測る重要指標です。スタートアップ業界では、過去に連続起業や上場経験を持つ創業者が率いる企業ほど、VCからの信頼も厚く、事業成長の可能性が高い傾向があります。
2. 情報収集に活用できる信頼性の高い情報源
■ TechCrunch/Forbes JAPAN/日経スタートアップなどのニュースメディア
資金調達・事業提携・IPOなどの一次情報が報道されるため、企業の成長トレンドを把握しやすいメディアです。特にTechCrunch JapanやINITIAL(ユーザベース社)ではスタートアップ情報に特化した詳細な企業分析を読むことができます。
■ Wantedly/OpenWork/YOUTRUSTなどのSNS型プラットフォーム
社員の価値観や企業文化を知るには、公式発信よりも、社員や関係者が記載するコンテンツの方が信憑性が高い場合があります。実際に働く人の声を拾えるコンテンツ(ストーリー投稿や口コミ)を複数比較することで、雰囲気のミスマッチを防げます。
■ ピッチ動画・登壇イベントアーカイブ
YouTubeやIVS(Infinity Ventures Summit)、JSSA、B Dash Campなどのピッチイベントで、CEOがプレゼンする姿をチェックするのも有効です。スタートアップは経営者の「人柄」と「語るビジョン」に左右される面も大きく、言葉の説得力や一貫性は事業の信頼度を測る材料になります。
■ VC・アクセラレーターの投資実績ページ
企業単体での判断が難しいときは、誰が投資しているかを見ましょう。日本の有力VC(例:ジャフコ、グロービス・キャピタル、WiL、ANRI、UTECなど)や海外ファンドが投資しているスタートアップは、一定の基準をクリアしている場合が多いです。
3. 信頼できる相談先の選び方
スタートアップ業界は変化が早く、求人票だけではわからない実態が多いため、相談できる相手を持つことがキャリアの明暗を分けます。
■ スタートアップ専門のキャリアエージェント
大手エージェントでは取り扱いの少ない“ハイレイヤー求人”や“経営直下ポジション”を網羅的に把握しているのは、スタートアップ専門の人材紹介会社やハイクラス転職エージェントです。彼らはVC・PEファンドとの独自ネットワークを持ち、求人の背景やカルチャー、CEOの人物像まで把握しているケースが多いため、ミスマッチを防ぎやすくなります。
■ 業界出身者・元スタートアップ勤務者
リアルな声を聞くには、過去にスタートアップに在籍していた人との接点をつくるのも有効です。LinkedInやYOUTRUSTなどを通じたOB訪問の申し出は、意外と快く受け入れてもらえることも多く、業界特有の「裏事情」を知る手段になります。
■ グロースタレントのようなVC出資先特化メディア
後章でも詳述しますが、VC・PEファンドの出資先に特化したハイクラス向け求人メディアでは、独自の非公開求人や経営陣直結ポジションの情報を得ることが可能です。また、キャリアアドバイザーも業界動向に精通しているため、単なる求人紹介ではなく“事業とキャリアの両面”からの支援が受けられる点が特徴です。
グロースタレントで描く、あなただけのスタートアップキャリア戦略
ここまでの章を通して、スタートアップという働き方の魅力、向き不向き、情報収集の重要性について見てきました。本章では、それらを踏まえてあなたのキャリアをどのように最適化するか、そしてそれを強力に支援してくれるサービス「グロースタレント」の活用法を紹介します。
1. VC・PEファンド出資先に特化した唯一無二の転職媒体
グロースタレントは、VC(ベンチャーキャピタル)・PE(プライベートエクイティ)ファンドが出資するスタートアップ・ベンチャー企業のみを掲載対象とした、ハイクラス転職プラットフォームです。
多くの人が「成長性のあるスタートアップで働きたい」と考えていますが、資金調達の有無や投資家の目利きがその企業の“将来性”を測る有力な指標となるのは事実。グロースタレントでは、投資家から見て“選ばれた企業”だけに絞って求人を掲載しているため、候補者にとっても安心して転職先を選べる仕組みが整っています。
2. 一般には出回らない経営直下ポジションの情報を網羅
グロースタレントには、以下のような「ここでしか出会えない求人」が多数掲載されています。
- 代表直下のCxO候補ポジション
- VC支援の元での経営企画・事業開発職
- シリーズB〜C以降の上場準備フェーズ企業の管理部門ポジション
- プロダクトオーナーや0→1フェーズのPdM職
こうした求人は、大手転職サイトでは表に出ることが少なく、また自らのネットワークだけでは到達できない領域です。グロースタレントでは、ファンドや企業経営陣とのパイプを活かし、信頼性の高いハイクラス求人を直接届ける体制が整っています。
3. 30〜40代のセカンドキャリア設計に特化した支援体制
20代だけでなく、「次こそ本当に納得できるキャリアを描きたい」と願う30代・40代にもグロースタレントは最適です。
この世代は、マネジメント経験や事業責任を持った経験が豊富である一方、「何を軸にキャリアを選ぶか」「自分に合ったフェーズのスタートアップとは何か」といった“棚卸しと再設計”が必要なタイミングでもあります。
グロースタレントでは、スタートアップ経験者・事業家出身者など多様なバックグラウンドを持つキャリアアドバイザーが在籍し、単なる職務経歴の擦り合わせではなく、キャリアの価値観設計から伴走します。いわば「転職支援」ではなく「キャリア戦略支援」です。
4. あなたの人生にスタートアップの選択肢を
スタートアップへの転職は、挑戦であると同時に、自分自身の市場価値を再定義し、ビジネスの中枢で手触りある成長を得る機会でもあります。
「自分にできるだろうか」と不安に感じる方こそ、一度グロースタレントを通じて、VC出資先という選び抜かれたスタートアップに触れてみてください。
可能性は、“正しく見極め、正しく繋がる”ことで大きく広がります。あなたの次のキャリアを、より戦略的に。より自分らしく。
グロースタレントで、あなたのスタートアップキャリアを拓こう
人生における「働く」という選択。その選択肢に、スタートアップという可能性を持ち込むことは、今後のキャリアを圧倒的に豊かにします。
あなたも、ただの転職ではなく「戦略的なキャリア構築」を目指しませんか?
スタートアップに強い、そしてあなたの可能性に真剣に向き合う。そんな場所が、ここにあります。
-

2025.10.24
スタートアップ
スタートアップ転職が40代でも遅くない理由|キャリア再設計で後悔しない選び方
40代のキャリアにとって「安定」と「挑戦」の狭間で揺れる今、スタートアップ転職は決して“遅い選択”ではありません。本記事では、40代が直面する不安やリスクを踏まえながら、経験を「変換力」として生かす方法、スタートアップで求められるマインドや行動、そして転職を成功へ導く意思決定のポイントを具体的に解説します。40代だからこそ描ける“再成長のキャリアストーリー”を、現実的かつ前向きに再設計するための一…
-

2025.09.08
スタートアップ
スタートアップ転職の失敗は「知らない」から起きる|後悔を防ぎ、成功に直結する思考法
「スタートアップ転職」に興味はあるものの、「失敗したらどうしよう」という不安から、一歩を踏み出せずにいませんか? この記事では、転職の失敗の本質が「情報の非対称性」にあると喝破し、その漠然とした不安を「キャリアへの確信」に変えるための全知識を、専門家の視点から徹底的に解説します。 この記事で分かること 多くの人が陥りがちな「失敗の共通パターン」と、スタートアップが持つ「構造的な…
-

2025.08.08
スタートアップ
「スタートアップはやめとけ」は嘘?後悔しない人が知る5つのメリットと優良企業の見極め方
スタートアップ転職に興味があるものの、「やめとけ」という声に不安を感じていませんか?本記事では、後悔しないために知るべきメリット・デメリットから、プロが実践する「優良企業の見極め方」までを徹底解説。漠然とした不安を解消し、自信を持ってキャリアの大きな一歩を踏み出すための、具体的な道筋を示します。 スタートアップ転職|その魅力と「やめとけ」の声の狭間で悩んでいませんか? 「自分のキャリア…
-

2025.07.09
スタートアップ
30代転職は”伸びる企業”を選べ。 VC・PEファンド出資のベンチャー企業に注目すべき5つの理由
30代転職が増えている理由とは?|変化するキャリア観と企業のニーズ 「30代で転職なんて早すぎる」──その"常識"は、もう古い かつて30代の転職には「もう遅い」「リスクが高い」といった慎重論がつきものでした。しかし現在ではむしろ、30代こそ転職の主戦場とされる時代に突入しています。 実際、厚生労働省の『令和5年 雇用動向調査』によると、2023年における30〜34歳の転職入職率…
